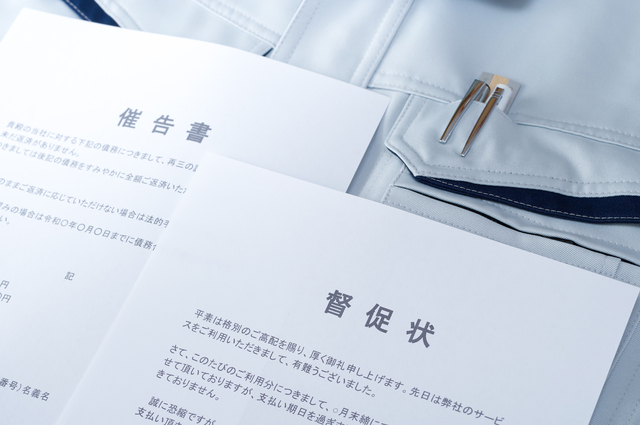
借金が返せない状態が続くと、銀行やローン会社、金融機関や貸金業者から返済を求める「督促状」が届くことがあります。この督促状を無視し続けると、最終的には資産が差し押さえられる恐れもあります。
もし督促状に記載されている内容通りの返済が難しい場合は、弁護士や司法書士に相談することを検討してください。
本記事では、以下の内容について分かりやすく説明していきます。
・督促状とは何か
・他の通知文書との違い
・督促状を無視した場合の結果
・督促状を受け取った時の正しい対応方法
・支払いが困難な場合の解決策、督促状でお悩みの方は、ぜひこの記事を最後までお読みください。
督促状や似たような書類
督促状と似た書類として「催告書」と「支払督促」がありますが、それぞれ目的や法的な意味が異なります。
この記事では、督促状と混同されやすい「催告書」と「支払督促」の違いについて詳しく解説していきます。
催告書
催告書とは、債権者が債務者に対して、債務の履行を求めるために発行する正式な書類です。主に、契約や法律に基づく義務を果たしていない場合に送付され、特定の期限内に支払いを求める内容が記載されています。催告書は、法的手続きが進む前の段階として位置付けられており、債務者に対して支払いを促す重要な役割を果たします。
催告書が送付された場合、債務者はその内容を真剣に受け止める必要があります。催告書には支払い期限や金額、振込先などの詳細が明示されているため、適切に対応しない場合、最終的には法的措置が取られるリスクが高まります。
このように、催告書は債務の履行を促すためのものであり、その存在を軽視することはできません。債務者はこの書類を受け取った際に、早急に確認と対応を行うことが重要です。
【催告書の特徴】
法的効力を持つ書類: 催告書は、債務者に債務履行を強く求めるものであり、法的根拠に基づいた書類です。
履行期日の明確化: 催告書には、債務履行を期日までに履行するよう、具体的な期日が記載されます。
法的措置の予告: 債務者が期日までに債務を履行しなかった場合、債権者は法的措置をとることを明確に予告します。
【催告書の必要性】
債務不履行による損害賠償請求や契約解除などの法的措置を行うための前提条件となる場合がある: 契約によっては、法的措置を行う前に催告書を送付する必要がある場合があります。
債務者に履行を促す効果: 催告書を送付することで、債務者に債務履行を強く促すことができます。
法的証拠となる: 催告書は、将来、法的紛争が発生した場合に、証拠として役立ちます。
【催告書の届き方】
催告書は通常、内容証明郵便という方法で送付されます。これは「いつ、どのような内容の文書が、誰から誰に送られたか」が記録として残るためです。この記録は、将来の裁判で「いつ、どの内容の文書が送られたのか」という事実を証明するために必要になることがあります。そのため、催告書を送った債権者は、将来的に訴訟を検討している可能性があることを示しています。催告書が手元に届いた際には、法的措置を取られないためにも早急に対応する必要があります。
支払督促
支払督促とは、債権者が債務者に対して、未払いの債務の支払いを促す法的手続きの一つです。この手続きは、主に金銭債務に関連しており、債権者が迅速かつ円滑に債務の回収を図るための手段として利用されます。
支払督促は、日本では簡易裁判所で行われる手続きであり、裁判所が発行する「支払督促状」によって債務者に通知されます。この通知が送られることで債務者は、指定された期間内に支払いを行うか、異議申し立てをする必要があります。債務者が期限内に支払いを行わない場合、債権者は強制執行手続きを進めることができるため、支払督促は債権回収の強力な手段となります。
なお、支払督促は、相手方が支払いを拒否している場合や、支払いが遅延している場合に適用されることが多いですが、事前に円満な解決を試みることが望ましいでしょう。債権者は、この手続きを進めることで、法的に認められた権利を行使し、債務者に対して支払いを求めることができます。
【支払督促の主な特徴】
債権者の一方的な申し立てにより手続きが進められ、債務者の審尋(尋問)は行われません。
債務者は支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申し立てをすることができます。異議申し立てがあった場合は、通常の訴訟手続きに移行します。
異議申し立てがない場合、支払督促は確定し、判決と同じ効力を持つ債務名義となります。
債務名義を得た後は、強制執行の手続きを取ることが可能となります。
【支払督促の届き方】
支払督促は、法的効力を有する点において、上記の督促状や催告書と本質的に異なる重要な文書です。これは裁判所から送付されるものであり、特別送達という手段を用いて届けられ、通常は郵便ポストには投函されず、郵便配達員から直接手渡されます。
支払督促を受け取った場合は、速やかな対応が求められます。受け取りから2週間以内に、異議申立てを行うか債務の支払いを完了する必要があります。この期間を過ぎると、仮執行宣言が出され、財産差押えの手続きが進んでしまいますので、迅速な対応が求められます。
督促状を無視するとどうなるのか?
督促状が届いても返済が難しい場合、無視したいと考えることがあるかもしれません。しかし、督促状を無視し続けると、状況はどんどん悪化していきます。以下のような段階を経て状況がさらに悪化してしまう可能性を解説します。
繰り返される督促状や督促電話が鳴る不安
延滞すると、まず文書による督促から始まり、その後電話による催促も加わってきます。返済期限を過ぎてから約1週間後に最初の督促状が届くことが一般的で、その際は比較的穏やかな文面で未払いの請求がされます。しかし、この督促状を無視すると、その後も連続して督促状の送付や電話連絡の頻度が増加し、徐々に返済を求める態度が厳しくなっていくのです。
このような状態が約1ヶ月続いても返済が行われない場合、元金と利息に加えて遅延損害金を含む督促状が送られてきます。遅延損害金は、借金の返済が遅れた場合に返済期日の翌日から課される損害賠償金で、遅れた金額に対して利息のように一定割合が加算されていきます。返済が遅れるほど、この金額は増加します。
遅延損害金には法律で上限金利が定められており、消費者金融からの借入の場合は年利20%が上限です。これは大きな負担となる可能性があるため、十分に注意が必要です。
連帯保証人に迷惑をかける
連帯保証人を立てて借りたお金に関する督促状を無視すると、およそ2ヶ月後には連帯保証人に支払い請求が及ぶ可能性があります。
連帯保証人は、主たる債務者(借り手)への請求を優先するよう求める権利や、複数の保証人間で債務を分割するよう要求する権利がないという点で、一般の保証人とは大きく異なります。債権者からの請求があった場合、連帯保証人は借り手本人と同等の返済義務を負うことになります。
このような事態に発展すると、あなたの借金問題によって連帯保証人の生活にも深刻な影響を及ぼすことになりかねません。
ブラックリストに登録!信用情報に傷が付く
借金の返済が遅れてから約2ヵ月が経過すると、信用情報機関にブラックリストとして登録される可能性があります。信用情報機関は、クレジットカードや借入に関する契約内容や返済状況を管理する機関です。金融機関や貸金業者は、借入の申し込み時にこの信用情報を確認し、融資の可否を審査します。
返済が滞ると、信用情報機関に事故情報として記載され、この状態がいわゆるブラックリストに載るということです。一度事故情報が登録されると、その後に返済を行っても、5年間はその情報が残るため、借金の支払いを2ヶ月以上延滞すると、信用情報機関のデータベースに延滞者として記録されてしまいます。
信用情報機関は、個人の借入履歴やカード利用状況、返済実績などの信用に関わる情報を一元管理する組織です。金融機関は、融資やカード発行の審査時に、この信用情報を参照して可否を判断します。
もし返済が遅れると、その事実が信用情報機関に「事故情報」として登録されます。これは一般的に「ブラックリスト入り」と呼ばれる状態です。
特に注意すべき点は、一度事故情報として登録されると、後で返済を完了しても、その記録は5年間消えないということです。この間、新規のローンやクレジットカードの契約が著しく困難になるため、カードや借入の申し込みに影響を及ぼす可能性がありますので、十分に注意が必要です。
催告書で一括返済を要求される
借金の返済が約2ヵ月遅れると、債権者から催告書という正式な通知が送付されることが有ります。この書面では、元金、利息、遅延損害金の一括返済を求められ、期限内に返済が行われない場合は法的措置を取る可能性があると警告されるのが通常です。一般的に、催告書は内容証明郵便で送られてくるため、受け取ったにもかかわらず「受け取っていない」と主張することはできません。
裁判所より訴状または支払督促が送付される
催告書で定められた支払期限を過ぎても返済がない場合、債権者は法的措置に移行するのが一般的です。通常、滞納から約3ヵ月後に、裁判所から特別送達で「訴状」か「支払督促」のいずれかの書類が送られてきます。
「訴状」を受け取った場合は、裁判手続きが開始されたことを意味し、裁判所への出頭や答弁書の提出等の対応が求められます。
一方、「支払督促」は裁判所からの支払命令であり、財産の差押えを回避したい場合には、受け取りから2週間以内に異議を申し立てる必要があります。
財産の差し押さえ
法的書類である訴状や支払督促を受け取った際、正しい対応を取らないと、債権者が請求する金額が確定判決となってしまいます。その結果、債権者は未払いの金額を差押えを通じて強制的に回収できることになります。具体的には、銀行口座の預貯金、給与の一定部分、土地・建物などの不動産、自動車、手持ちの現金といった財産が差押えの対象となります。
督促状受領後の対処法
督促状を無視し続けると、財産がない方でも最終的に遅延損害金が発生し、給料が差し押さえられる可能性があります。給料が差し押さえられると、借金があることが会社に知られることになるため、早急に適切な対処が求められます。
ただし、焦って督促状の要求通りに支払うことが、必ずしも最善の選択とは限りません。むしろ、状況を慎重に見極めた上で適切な対応を取ることが重要です。
催促状が本物か?確認する
督促状を受け取った際の最優先事項は、その請求が正当なものか架空のものかを見極めることです。近年、実在しない債務を根拠に金銭を要求する詐欺行為が増加しており、警察庁や国民生活センターも市民に対して警戒を呼びかけています。
もし届いた督促状に全く心当たりがない内容が記載されていた場合には、無視しても問題ありません。ただし、発送元の会社名が記憶にないからといって、必ずしも無視するべきではありません。たとえば、遅延している借金を肩代わりしてくれた保証会社や、借入先から依頼された債権回収業者からの督促状も考えられますので、督促状を受け取った際は、記載内容を慎重に精査することが重要です。
督促状が本物かどうかを確認するためには、以下のいくつかの方法を試みることができます。
・送信者の確認:督促状に記載されている送信者の会社名や連絡先をチェックし、公式ウェブサイトや電話帳でその会社が実在するか確認します。
・連絡先に問い合わせる:督促状に記載されている電話番号やメールアドレスに直接連絡し、督促状の発信元であるか確認します。注意点として、督促状に記載されている連絡先からではなく、公式な情報を元に連絡することが重要です。
・内容の確認:督促状に記載されている金額や詳細が正しいか、自分の記録と照らし合わせて確認します。
・郵送物の形式:確認済みの正式な文書であるか、レターヘッドや署名、印章など、正式な形式が整っているかをチェックします。
・法律的なアドバイスを求める:不安な場合は、法律の専門家に相談することも良い考えです。特に、支払うべき金額に疑念がある場合は、専門家の意見を聞くことが重要です。
・消費者センターや弁護士に相談:不審な督促状に対する相談窓口がある場合、そこで相談することも有効です。
心配な場合は、迅速に行動を起こし、冷静に対応することが大切です。
債権者の情報と取引期間の確認
督促状が本物であり、架空請求ではないことが確認できたら、次に債権者の情報と取引の期間を確認する必要があります。
特に、クレジットカード会社との取引が長期に及ぶ場合は注意が必要です。利息制限法で規定された金利の上限を超えて支払いを続けていた可能性があり、この超過分は「過払い金」として認定されます。過払い金が存在する場合、既存の債務額を減らせる可能性があるだけでなく、場合によっては返還請求を行うことも可能です。
【過払い金】
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社から借り入れを行った際に、利息制限法に基づいて払いすぎた利息のことを指します。過去に利息制限法によって設定された利率を超えた利息を請求されることがあり、その結果、借り手は本来支払うべきではない過剰な利息を支払ってしまうことがありました。
2010年に完全施行された貸金業法により、貸金業者が請求できる金利の上限は年利20%までと定められています。それ以前は、いわゆるグレーゾーン金利(年利20%~29.2%)での貸付けが行われており、多くの借り手が高金利での返済を強いられていました。
過払い金は、2006年頃から問題として注目されるようになり、多くの利用者が自分の過払い金を確認し、返還を求めるために法的手続きを進めるようになりました。返還請求が認められると、借り手は過払い金とその利息を受け取ることができるため、多くの人々にとって経済的な救済となります。
過払い金の請求には時効があります。過払い金請求を行っていない方や過払い金が発生しているか分からない方は、「過払い金の無料診断」を行っている弁護士事務所に相談する事をお勧めします。
当事務所では、過払い金の無料診断を行っておりますので、お気軽にお問合せください。
借金の時効確認とその援用
過払い金の確認を行った結果、まだ借金が残っている場合は、「消滅時効制度」の利用が可能かどうかを調べる必要があります。この制度は、借金の返済が滞った状態が続き、最後の返済日から5年以上経過しているにもかかわらず、債権者から請求がなければ、借金の返済義務(債務)が消滅するというものです。そのため、督促状が届いた際には、どの時点から返済が行われていないのかを確認することをおすすめします。
ただし、注意すべき点として、単に5年という期間が経過しただけでは債務は自動的には消滅しません。時効による債務消滅の効果を得るためには、債務者自身が「時効を援用する」という法的手続きを行う必要があります。
【消滅時効制度】
消滅時効制度とは、一定の期間が経過することによって、法律上の権利や義務が消滅する制度のことを指します。日本の民法においては、消滅時効は主に請求権に適用され、権利者がその権利を行使しないまま所定の期間が経過すると、権利の行使ができなくなります。これにより、権利の不安定状態や訴訟の長期化を防ぐ目的があります。
消滅時効の期間は権利の種類によって異なります。
・一般の債権:10年
・商事債権:5年
・不法行為に基づく損害賠償請求権:3年 などと定められています。
また、時効の完成を阻止するためには、権利者が権利を行使する意思を示す「時効の中断」という手続きが必要です。裁判上の請求や差押え、債務の承認などがこれに当たります。
なお、2020年4月の民法改正により、「時効の中断」は「更新」に、「時効の停止」は「完成猶予」に用語が変更されるなど、制度の現代化が図られています。
期限内に返済する
正当な債務であり時効による解決も難しい場合、督促状に示された支払期限を守る必要があります。期日までに支払いができないと、延滞金が上乗せされ、財産の差押えなどの法的措置を受けるリスクが増すため、できる限り全額を工面する方法を真剣に考える必要があります。
督促状に従った返済が難しい時の対応策
督促状が届いた際には、できるだけ早く返済することが最も望ましい対応ですが、もし督促状に記載された通りの返済が難しい場合は、借金問題に詳しい弁護士に相談し、債務整理という選択肢を検討することで、解決の糸口が見つかるかもしれません。
債務整理とは、返済が困難になった場合に、債権者と交渉したり、裁判所に関与してもらうことで、借金額を減らしたり支払いを猶予してもらう手続きのことです。債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があり、それぞれに異なる特徴があります。
債務整理による3つの借金解決方法
1.任意整理
任意整理とは、借金返済に困っている人が債権者と直接交渉し、現在の返済条件を見直して、無理のない返済計画を立てるための手続きです。この手続きは法律の枠組みではなく、あくまで債務者と債権者との間で合意に基づいて行われるため、「任意」の整理と呼ばれています。
任意整理では、通常、利息や遅延損害金のカット、返済期間の延長などにより、月々の返済負担を軽減します。この手続きは裁判所を介さずに行うため、個人に与える影響が比較的少なく、手続きも迅速に進められることが特徴です。
手続きは、弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼して進めることが一般的です。専門家が債権者との交渉を代行することで、借金の負担を軽減し、合理的で現実的な返済プランを構築します。また、手続きの開始と同時に返済が一時ストップされることが多く、精神的な負担の軽減にも寄与します。
ただし、任意整理はあくまでも双方の合意に基づくものであり、交渉が不調に終わることもあります。また、整理後の返済計画に従って返済を行う必要があるため、新たな計画にもどることがないように注意が必要です。この手続きは、特に自己破産を避けたいと考える人にとって、有効な借金整理の方法の一つとされています。
【任意整理の主な特徴】
≪メリット≫
・裁判所を介さないため、手続きが比較的迅速
・手続き費用が法的整理と比べて安価
・財産の処分を強制されない
・債務者の意向を反映させやすい
≪デメリット≫
・債権者全員の同意が必要
・債権者との交渉が不調に終わる可能性がある
・商品の購入や借入などの与信が制限される可能性がある
【任意整理の一般的な手続きの流れ】
・専門家への相談、依頼
・債務の状況確認と整理
・債権者との交渉開始
・和解契約の締結
・返済計画に基づく支払いの実行
【任意整理で実現できる主な内容】
・返済額の減額
・返済期間の延長
・金利の引き下げ
・債務の一部免除
・分割払いへの変更
なお、任意整理は全ての債務問題に適しているわけではなく、債務の総額や返済能力によっては、個人再生や自己破産などの法的整理を検討する必要がある場合もあります。
【任意整理を検討する際は、以下の点に注意が必要です】
・債務の総額と返済能力の確認
・債権者数と債権者との関係
・保証人の有無と対応
・将来の収入見込み
・他の債務整理手段との比較検討
このように、任意整理は比較的柔軟な債務整理方法ですが、成功のためには専門家のサポートを受けながら、慎重に進めることが推奨されます。
2.個人再生
個人再生とは、債務整理手続きの一つで、収入はあるものの多額の借金を抱えて返済が困難になった個人が、裁判所を通じて借金の減額を図り、新たに再スタートを切ることを目的とした制度です。この手続きは、借金の総額を大幅に減額してもらうことにより、債務者が無理のない範囲で返済計画を立て、その計画に基づいて返済を続ける方法です。個人再生には主に「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という二つの種類があり、それぞれに適用条件や手続き内容が異なります。
小規模個人再生は、主に中小規模の借金を抱えた個人が対象で、債権者の過半数の同意を得ることが求められます。一方、給与所得者等再生は、安定した収入を持つサラリーマンなどの個人が対象で、債権者の同意は必要なく、収入の一定割合で返済計画を立てることができます。
個人再生のメリットとしては、自己破産とは異なり借金が全てなくなるわけではありませんが、住宅ローン特則を利用して自宅を手放さずに済む場合もあります。ただし、手続きが複雑で時間がかかることや、裁判所の認可が必要なため支払能力をしっかりと証明する必要があります。
この手続きは複雑な為、弁護士や司法書士といった専門家のサポートを受けながら進めることが一般的であり、個人再生を選択する際には適切な専門家に相談し、自分にとって最適な解決方法を見つけることが重要です。
【対象者】
・給与所得者や個人事業主
・安定した収入がある個人
・債務が返済能力を超えている人
≪メリット≫
・債務の一部免除が可能
・一定の財産を保持したまま再建できる
・住宅ローンの継続が可能
【手続きの流れ】
・弁護士への相談
・裁判所への申立て
・再生計画案の作成
・債権者の同意と裁判所の認可
・計画に基づく返済の実行
【必要な条件】
・安定した収入があること
・返済計画を履行できる見込みがあること
・破産手続きよりも債権者に有利な返済ができること
【注意点】
・弁護士費用が必要
・手続きに数ヶ月かかる
・計画通りの返済が必須
・信用情報に記録が残る
個人再生は、破産とは異なり全ての借金を帳消しにできません。生活再建を図れる制度として注目されています。ただし、専門的な知識と手続きが必要なため、弁護士に相談することが推奨されます。
3.自己破産
自己破産とは、個人が多額の借金を抱えて返済が困難になった場合に、法的手続きを通じてその債務を免責してもらうための制度です。自己破産を申し立てると、裁判所は申立人の全資産を清算し、債権者に対して可能な限りの返済を行った上で、残る債務の免責を決定します。これにより、申立人は実質的に過去の借金から解放され、新しい生活を始めるためのスタートを切ることが可能となります。
ただし、自己破産にはいくつかのデメリットもあります。例えば、一定の職業資格の制限がかかる場合があるほか、信用情報に破産の記録が長期間残るため、新たなクレジットカードの取得やローンの審査が通りにくくなることがあります。また、手続きには時間や費用がかかるため、専門家による事前の相談や準備が不可欠です。
自己破産は最終手段と見なされるべきものであり、可能であれば他の解決策を検討することが推奨されます。例えば、任意整理や個人再生といった他の債務整理の方法にも目を向けることが考えられます。このような選択肢を検討する際には、信頼できる弁護士や司法書士の専門家にアドバイスを仰ぐことが重要です。いずれにせよ、自己破産は経済的な再スタートを切るための貴重な一歩となり得る制度であることは間違いありません。
【自己破産には以下のようなメリットとデメリットがあります】
≪メリット≫
・借金の支払いが免除される
・給料や財産の差し押さえが停止される
・債権者からの取り立てがなくなる
≪デメリット≫
・信用情報への影響:自己破産をすると、その情報が信用情報機関に登録されます。この情報は約7年から10年の間、金融機関やクレジットカード会社に通知されるため、新たな借入やクレジットカードの取得が難しくなります。
・資産の喪失:自己破産時には、借金の返済を免れる代わりに、一部の資産が処分されることがあります。これには不動産、車両、貯蓄などが含まれる可能性があります。
・職業制限:一部の職業(弁護士、公認会計士、金融業など)では自己破産をしていると、その職業に従事できない場合があります。
・館報に名前と住所が掲載される
・破産者名簿に記載される
手続きを進めるには、まず弁護士に相談し、必要書類を準備して裁判所に申し立てを行います。その後、裁判所による審査を経て、免責許可の決定が下されます。
ただし、自己破産は安易に選択すべき選択肢ではありません。弁護士や司法書士に事前に相談して任意整理や個人再生など、他の解決方法も検討することが望ましいでしょう。
※この3つの方法のいずれを選ぶかは、収入の状況や返済可能額、さらには債務の総額などに応じて変わります。いずれの方法でも、破産法や民事再生法に関する専門知識や金融機関との交渉力が求められるため、弁護士に相談するのが一般的な手順となっています。
督促状が届いたら早急に弁護士に相談しよう
督促状が届いたからといって、すぐに差押えが行われるわけではありません。しかし、催告書や支払督促が届く段階になると、差押えのリスクが迫っているため、迅速な対応が求められます。督促状を無視していると、遅延損害金が加算され、支払うべき金額が増えてしまいます。催告書や支払督促を放置すると状況がさらに複雑化する恐れがあるため、注意が必要です。もしすぐに返済が難しい場合は、債務整理を検討する必要があります。
当法律事務所では、多くの借金問題を解決してきた実績があります。お客様の状況を丁寧に確認し、最適な解決方法をご提案いたします。一人で抱え込まず、まずはご相談ください。借金問題に関するご相談は何度でも無料で承っております。お気軽にお問合せください。
最後に
借金の返済が遅れると、催告書や支払督促といった通知が送付されることがあります。また、自宅や職場、携帯に連絡が来ることもあります。その際、一人で対応するのは難しいことがあると思いますので、その際は一人で対応するのではなく、ぜひ弁護士を頼ってください。
当事務所では、あなたの個別の状況に合わせて、最適な解決方法をご提案いたします。まずは、現在の生活状況や収入状況などを丁寧にお伺いした上で、任意整理や個人再生、時効援用手続きや自己破産など、最も適切な債務整理の手段をご案内いたします。また、借金問題の相談は何度でも無料で受け付けており、債務整理にかかる費用についてもできる限り分割で対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

