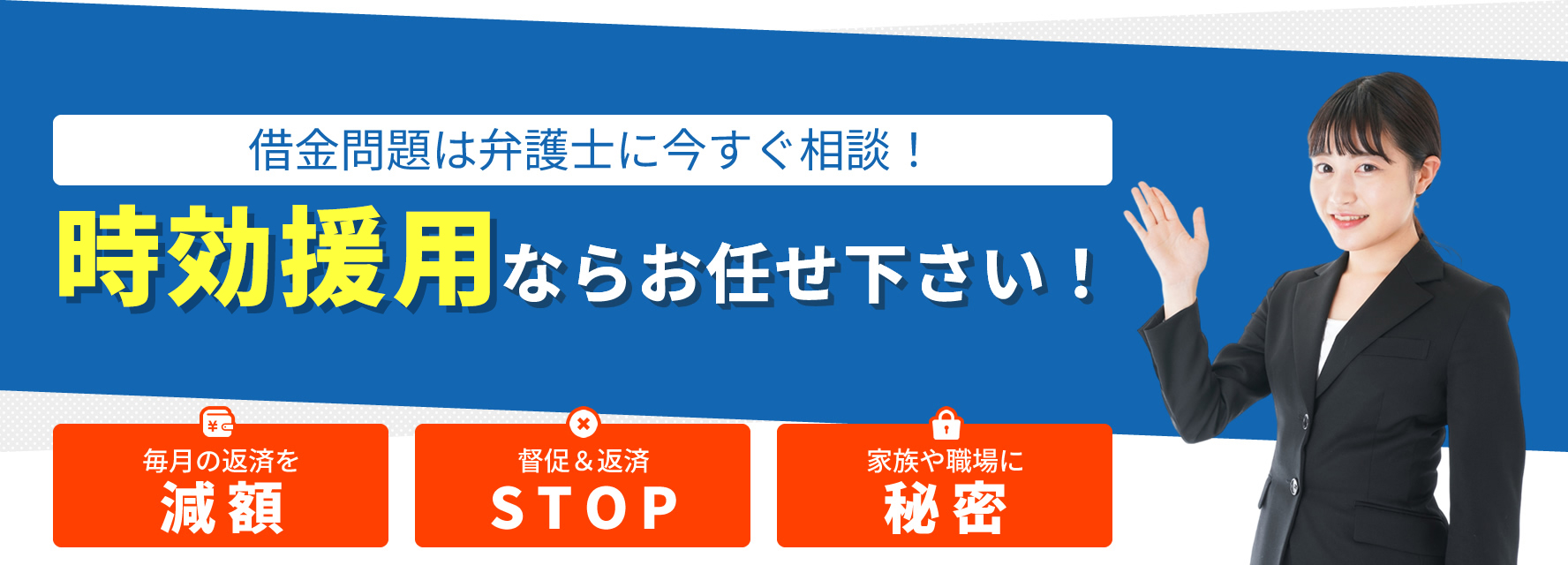
法律で定められた「借金の消滅時効」制度を活用すれば、特定の条件下で返済義務から解放される可能性があります。
この制度は、一定期間が経過した債務を法的に消滅させる仕組みですが、適用には具体的な要件を満たす必要があります。
この記事では、借金の消滅時効に関する基本情報や、時効が完成するための要件、知っておくべき注意事項、さらに時効以外の借金解決策について詳しく説明します。
借金の消滅時効に関する基本情報
目次
借金の消滅時効とは、債権者が債務者に対して請求や通知をしないまま、法律で定められた一定の期間が経過すると、債権者の法的権利が消失する制度です。要するに、所定の期間が経過すると債務者は借金を返済する義務を免れることになります。
消滅時効の完成に関する期間については、2020年4月に施行された民法改正により、新たなルールが導入されました。具体的には、「債権者が権利を行使できることを知った時点から5年間、その権利を行使しなかった場合」または「権利を行使できる時点から10年間、その権利を行使しなかった場合」のどちらか短いほうの期間が経過した場合に、時効が成立します(民法第166条)。
金融機関や貸金業者からの借金については、契約書に返済期日が明示されているため、債権者は返済期日が来ると権利を行使できることを知っていると見なされます。このため、通常は5年が消滅時効の期間(時効期間)となります。
なお、改正前の制度では、金融機関や貸金業者からの借金の時効期間は5年であり、個人間の借金は10年とされていました。業者からの借金に関する消滅時効の期間は変更されていませんが、個人間の借金に関する期間は2020年の改正により変更されました。したがって、2020年4月1日以前に発生した個人からの借金の時効期間は、基本的に改正前の民法が適用され、10年のままとなります。
借金の消滅時効制度は、債権者からの請求や通知がないまま一定期間が経過した場合、債務者の借金返済義務を法的に消滅させることができる仕組みです。
◆2020年4月の改正民法により、時効の完成期間は以下のように定められました。
・債権者が権利行使可能と知った時点から5年間
・権利行使が可能となった時点から10年間 上記のうち、先に到来した期間で時効が成立します。
金融機関などの業者からの借金については、契約書に返済期日が明記されているため、通常5年で時効が成立します。これは改正前の制度と変わりありません。
◆一方、個人間の借金については変更がありました。
・改正前:一律10年
・改正後:上記の5年/10年ルールを適用
ただし、2020年4月1日より前に発生した個人間の借金については、従来通り10年の時効期間が適用されます。
時効が完成するための要件
借金の消滅時効が成立するためには、期間の経過だけでは不十分で、いくつかの条件を満たす必要があります。条件がすべて整っていることが求められます。
・法定の時効期間が経過していること
・債権者が権利を行使できる状態であったこと
・その間、債権者が権利行使をしていないこと
この条件が揃って初めて、借金の消滅時効が認められます。
5年もしくは10年支払いをしていない
借金の消滅時効が成立するためには、債権者が一定期間、自らの権利を行使しないことが前提となります。この消滅時効の開始時期は起算点として知られ、債権者が債権の回収を求められる日からカウントが始まります。一般的には、契約書などに明示された返済期限が基準となります。
【返済実績がない場合】 • 契約書に記載された最初の返済期日が起算点 • その日から5年間の経過で時効が成立する可能性
債務者が一切返済を行っていない場合、原則として契約書に記載された初回返済期日が時効の開始点になります。つまり、返済期日を過ぎてから5年が経過すると、その借金に関する債権者への返済義務が消滅する可能性があるのです。
【返済実績がある場合】 • 最終返済後の次回返済予定日が起算点 • その日から5年間の経過で時効が成立する可能性
一方で、債務者が一度でも返済を行っていたが、その後何らかの理由で返済を止めた場合は、時効のカウントは「最後の返済をした直後の返済期日」からスタートします。この最後の返済日から5年が経過すると、時効期間が満了することになります。
このように、時効の開始日は返済の状況によって異なるため、債務者が時効について確認する際には、返済履歴や関連記録を調査し、正確に時効期間を把握することが重要です。
重要なポイント: • 起算点は返済状況により異なる • 正確な時効期間の把握には返済履歴の確認が必要 • 時効の完成には他の要件も必要
なお、時効の成立には単なる期間経過だけでなく、その他の法的要件も満たす必要があります。
裁判、支払督促、および催告が実施されていない状態
債務の時効が成立するためには、債権者による裁判手続きや督促、催告といった法的アクションが取られていないことが必要です。時効の期間が過ぎていても、債権者が裁判などの法的手続きを行った場合、時効の進行は一時的に停止されたり、リセットされることがあります。
法律によって定められた理由により、時効の成立が一時的に停止し、延長される制度を「時効の完成猶予」と呼び、時効の進行がリセットされる制度を「時効の更新」と呼びます。借金に関する消滅時効においては、以下のような場合に完成猶予や更新が生じることがあります。
裁判を起こされている場合
債権者が債務者に対して訴訟を提起した場合、その訴訟が終了するまで時効は成立しません。借金の返済請求に関する裁判としては、例えば「給付の訴え」や、債権の有無を確認するための「確認の訴え」などがあります。訴訟が取り下げられた場合には、取り下げた日から6ヵ月の猶予期間が設けられます。
裁判で債権者の請求が認められ、権利が確定した場合は時効が更新され、新たな時効期間が開始します。特に重要なのは、この場合の時効期間が10年間と通常より長期に設定されている点です(民法第169条による)。
支払督促が申し立てられた場合
債権者が裁判所に支払督促を申し立てた場合、その手続きが進行中は時効は成立しません。支払督促は、債権者が債務者に対して金銭の支払いを求めるための法的手続きの一つです。裁判所は申立てを受けると、債務者宛に「支払督促」という文書を送付します。この文書は、金融機関や貸金業者が送る通常の督促状とは異なる法的な性質を持っています。
この書類が債務者に届いた場合、2週間以内に異議を申し立てなければ、債権者は仮執行宣言の申立てを行うことが可能になります。その申立てが受理され、仮執行宣言がされると、債権者は強制執行を行うことができるようになります。
さらに、債務者が異議を申し立てない場合、債権者の権利は確定し、その結果、時効期間がリセットされることになります。
強制執行が行われた場合
債権者が債務者に対して強制執行を行った場合、その手続きが続いている間は時効は成立しません。強制執行とは、裁判で勝訴したにもかかわらず判決に従った支払いが行われない場合に、債権者が裁判所を通じて手続きを進め、国家の権力を使って債務者の財産を差し押さえ、必要に応じてその財産を競売などで売却し、強制的に支払いを実現させるプロセスです。
強制執行が行われても全額の返済が完了しない場合、残りの金額についての時効期間はリセットされます。
仮差押えが行われた場合
債権者が裁判所に申し立てて仮差押えを行うと、債務者は対象となる財産を自由に処分できなくなります。これは債権者が債権を回収するために、債務者の財産を予め確保しておく法的手段です。
また、仮差押えが終了した後、6ヵ月間は時効の完成が停止されます。つまり、この期間中は債権の消滅時効が進行しないことになります。
催告書が届いた場合
債権者が債務者に対して支払い要求の催告を行った場合、その催告から6ヵ月の間は時効が進行しません。催告とは、債権者が債務者に返済を要求するための通知を指します。催告の方法に関して法律で特に定められているわけではありませんが、一般的には内容証明郵便が用いられます。この方法により「いつ、どのような内容の文書が、誰から誰に送付されたか」が記録に残ります。
催告書が届けられると、その後の6ヵ月間は時効が停止します。この期間中、債務者が何も行動を起こさなければ、債権者は支払い督促や裁判などの法的手続きを進めることが一般的です。したがって、催告書の受領は時効の成立を難しくする要因となります。
なお、上記の状況以外にも、天災が原因で裁判や強制執行が行えない場合なども、時効の進行が一時的に停止することがあります。
債務を承認する行動をしていない
時効の完成の条件として、債務を承認するような行動をしていないことも挙げられます。
債務者が債務の存在を明示的に認めるような行動をすると、時効の更新が起こり、時効期間をリセットさせることになってしまうため、注意しなければなりません。
具体的には、借金の一部返済、支払いの猶予の相談、示談などの行為が、債務の承認にあたります。
督促状などが届いた際に、時効期間の確認をせずに債権者に連絡して支払う意思などを見せてしまうと、もともと時効が完成していた場合であっても時効がリセットされてしまい、本来は返済する必要がなくなっていた債務を返済しなければならなくなるおそれがあります。
以下の行為は「債務の承認」とみなされ、時効期間が最初からやり直しになります
• 借金の一部返済 • 支払猶予の相談 • 示談交渉 • 支払う意思の表明
◆注意すべきポイント
• 督促状が届いても、すぐに債権者へ連絡しない
• 時効期間を確認してから対応を検討する
• 安易な対応で時効がリセットされる可能性がある
• 時効完成後の債務承認でも、再び支払義務が発生する
時効の利益を得るためには、債務承認と判断される行為を避けることが必要不可欠です。
知っておくべき注意事項
たとえ時効が完成していても、それだけではすぐに借金の返済義務(債務)が消滅するわけではありません。債務を消すためには「援用」という手続きを行う必要があります。
援用とは、債権者に「時効が成立しているため、返済を行わない」という意向を伝えることを指します。援用を行うことで、借金は消滅し、一部の信用情報機関からは事故情報が削除されます。また、自己破産に比べて手続きが簡便であることも特徴です。
援用の意思表示は口頭でも法的には問題ありませんが、口頭の場合は後々「言った、言わない」の争いに発展する可能性があります。
このようなトラブルを避けるために、「時効援用通知書」を内容証明郵便で送付することをお勧めします。
ただし、この「時効援用通知書」には、借金を特定できる情報をできる限り正確に記載する必要があります。また、債権者とのやり取りの中で誤って債務を承認するリスクも考慮しなければなりません。そのため、正確かつ適切に手続きを進めるためには、専門家である弁護士に依頼することが賢明です。
◆援用のメリット
• 債務が完全に消滅する
• 信用情報機関の事故情報が抹消される
• 自己破産より手続が簡単
◆援用の方法
• 債権者へ「時効完成による返済拒否」の意思表示
• 内容証明郵便での「時効援用通知書」の送付を推奨 (口頭での意思表示も有効だが、後日トラブルの原因となりやすい)
◆注意点
• 借金を特定する正確な情報が必要
• 手続中の不適切な対応で債務承認となるリスクあり
• 専門知識が必要な手続のため、弁護士への相談を推奨
時効以外の借金解決策
借金の消滅時効は、債務者側に大きな利点をもたらす制度ですが、その適用には厳しい条件があります。具体的には、債権者が返済期日から5年以上にわたって請求行為を行わないことなど、複数の要件を満たす必要があります。
しかしながら、時効を待つことだけが借金問題の解決方法ではありません。借金でお困りの方には、債務整理という選択肢があります。債務整理を利用すれば、借金額を軽減したり、無理のない返済計画を立てたりすることが可能です。
債務整理の方法は主に3種類あり、それぞれの状況に応じた対応が可能となっています。
任意整理
任意整理とは、借金を抱えている個人や企業が、債権者と直接交渉を行い、返済条件の見直しや減額を求める手続きのことを指します。この方法は、主に自己破産や個人再生といった法的手続きの代替手段として利用されます。任意整理の特徴は、裁判所を介さずに債権者と直接話し合いを行うため、比較的手続きがスムーズであることです。
任意整理を行う際は、まず借金の全体像を把握し、どのような返済計画を立てるかを決める必要があります。次に、信頼できる法律の専門家や債務整理の業者に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。その後、債権者に対して具体的な返済条件の変更を申し入れます。この過程で、利息の減免や返済期間の延長、一部借金の免除などを交渉することが可能です。
任意整理の利点としては、自己破産とは異なり、財産を保持できる点や、手続きが比較的短期間で済む点が挙げられます。また、信用情報の影響も自己破産より軽度であるため、一定の期間後には新たにクレジットカードやローンを利用できる可能性もあります。
しかし、任意整理を行うことで信用情報に事故情報が記録されるため、今後の借入れに影響が出ることがあります。また、債権者が必ずしも要求に応じてくれるわけではないため、一部の債権者との交渉が難航する場合もあります。
総じて、任意整理は借金解決の一つの手段として有効ですが、しっかりと弁護士や司法書士に相談し、自身の状況に合った最適な方法を選ぶことが大切です。
◆主な特徴
• 裁判所を介さない私的解決
• 債権者との合意が必要
• 費用が比較的安価
◆メリット
• 破産や個人再生と違い第三者に知られにくい
• 法的手続きと比べて手続きが簡便
• 柔軟な返済プランの設定が可能
• 債権者との関係を維持しやすい
◆デメリット
• 債権者が応じない可能性がある
• 債務の一部免除は難しい場合がある
• 信用情報に載る
• 破産などと比べて社会的な影響が少ない
※任意整理は、債務者の経済的再建を図りながら、債権者との関係も維持できる方法として、多くの人に選択されています。ただし、専門的な知識が必要なため、通常は弁護士や司法書士などの専門家に依頼します。
任意整理詳しくはこちら:https://big-market.jp/arbitrary/
個人再生
個人再生とは、日本の法律制度の一つで、経済的に困難な状況にある個人が、自己の財産を整理しながら再起を図ることを目的とした手続きです。この制度は、主に借金を抱えている人々を対象としており、一定の条件を満たすことで、債務の一部を減額したり、返済の猶予を受けたりすることが可能です。
個人再生の手続きは、主に以下のステップで進行します。まず、申立人は裁判所に個人再生を申し立てます。その際、収入や財産、借金の状況を詳細に記載した書類を提出する必要があります。裁判所はこれらの情報を基に、個人再生の適用が可能かどうかを判断します。
次に、個人再生計画を策定します。この計画には、どのように債務を返済していくのか、具体的な返済額や期間が明記されます。債権者の同意を得た後、裁判所の承認を受けることで、計画が正式に成立します。成立後は、計画に基づいた返済を行い、一定の期間が経過すると、残りの債務が免除されることになります。
個人再生のメリットは、債務整理が可能になるだけでなく、住宅ローンを抱えている場合でも、自宅を維持できる可能性がある点です。しかし、手続きには時間がかかることや、信用情報に影響を与えることもあるため、慎重に考える必要があります。
総じて、個人再生は、再び経済的自由を手に入れるための重要な手段であり、多くの人々にとって希望となる制度であると言えるでしょう。合法的な手続きに基づいて新たなスタートを切ることができるため、生活再建を目指す人にとって有効な選択肢となります。
◆主な特徴
• 住宅ローンを除く債務を大幅に減額できる
• 給与所得者であれば、原則として現在の仕事を継続できる
• 破産と異なり、資格制限がない
• 住宅を持っている場合、住宅ローンを完済することで自宅を手放さずに済む
◆申請要件
• 安定した収入がある個人であること
• 返済できない借金を抱えていること
• 破産手続き開始の原因となる事実の生ずるおそれがあること
◆手続きの流れ
• 弁護士への相談
• 裁判所への申立
• 再生計画案の作成
• 債権者集会での決議
• 裁判所による認可
• 再生計画に基づく返済の実行
◆メリット
• 大幅に債務の免除を受けられる
• 財産を保持したまま債務整理が可能
• 自己破産よりも社会的な信用を維持しやすい
◆デメリット
• 一定の費用が必要
• 手続きが複雑
• 債権者の同意が必要
• 3年から5年の返済計画を実行する必要がある
◆手続きを成功させるためには、以下の点に注意が必要です
• 収入の見通しを正確に立てる
• 適切な返済計画を策定する
• 必要な書類を適切に準備する
• 期限を守って手続きを進める
※個人再生は、経済的な再出発を図りたい個人債務者にとって有効な選択肢の一つとなっています。ただし、専門的な知識が必要となるため、通常は弁護士に依頼することが推奨されます。
個人再生詳しくはこちら:https://big-market.jp/personal/
自己破産
自己破産とは、個人が自らの財政的な負担に耐えられなくなった場合に、その債務を法的に免除してもらう手続きのことを指します。具体的には、借金が返済できない状況に陥った際に、裁判所に申し立てを行い、正式に自己破産を宣告されることで、残っている債務を免除される仕組みです。
自己破産には、いくつかのメリットとデメリットがあります。メリットとしては、返済義務から解放され、経済的な再スタートを切る機会を得られることが挙げられます。また、自己破産を申請すると、債権者からの取り立てが一時的に停止されるため、精神的な負担も軽減されることがあります。
一方、デメリットとしては、自己破産をすると信用情報にその事実が記録され、今後数年間は新たな借り入れやクレジットカードの取得が難しくなることがあります。また、財産の一部が処分される可能性があるため、大切な資産を失うリスクも伴います。
自己破産は、最終手段として考えられるべきものであり、可能であれば他の債務整理の方法を検討することも重要です。例えば、任意整理や個人再生などの手段を通じて、より良い解決策を見出すことができる場合もあります。
以上のように、自己破産は難しい決断であり、しっかりとした情報収集と弁護士の意見を参考にすることが大切です。経済的な問題に直面している方は、自身の状況を冷静に見極め、適切な対処を考えることが求められます。
◆主な特徴
• 裁判所による手続きが必要で、自分自身で手続きをしても費用は約20万円程度かかります。
• 破産が認められると、原則として債務が免責され、返済義務がなくなります。
• 手続き中は、給与の差し押さえや取り立てが停止されます。
◆以下の債務は免責されません
• 税金
• 養育費
• 故意の不法行為による損害賠償
• 詐欺や浪費によって作った債務
※なお、破産しても一定額の財産は手元に残すことができ(民事執行法上の差押禁止財産)、生活の再出発のための基盤は確保されています。
自己破産詳しくはこちら:https://big-market.jp/bengosi4/
時効が完成しているか?弁護士に相談しよう
時効の成立を判断するには、法律に関する専門的な知識と、債務の承認が行われていないかを確認するための事実調査が必要です。実際に時効を援用する手続きを進めるためには、専門知識を持つ弁護士の支援が不可欠です。弁護士に相談すれば、万が一時効が成立していなかった場合でも、債務整理に関するアドバイスや手続きのサポートを受けることができます。
当法律事務所は、豊富な借金問題解決の経験を持ち、時効の援用に関するサポートや、状況に応じた最適な債務整理の方法をご提案しております。借金問題でお悩みの方は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。
守秘義務
借金の時効が成立している場合、法定の手続きを経て債務を消滅させることができます。たとえ時効成立に至らない場合でも、ご相談いただいた内容は弁護士の守秘義務により厳重に保護されます。債権者に現在の勤務先や居所などの個人情報が漏れることは一切ありませんので、安心してご相談ください。
時効援用費用の相場
日本の弁護士における借金の時効援用手続きの費用は、依頼する弁護士や事務所、地域によって異なりますが、一般的な相場は以下のようになります。
◆着手金:通常、3万円から10万円程度が一般的です。ごく稀に、それ以上の金額を設定している場合もあります。
• 着手金:(初期費用)3〜10万円程度(1件あたり)
• 複数債権がある場合は、件数に応じて増額
◆成功報酬:時効援用が認められた場合、借金額に応じて成功報酬が設定されることがあります。これも一般的には借金額の10%から20%程度が相場です。
• 報酬金:時効消滅した債権額の10〜20%程度
• 債権額が少額の場合は、最低報酬額を設定していることもある
例)100万円の借金の場合
• 着手金:5万円
• 報酬金:20万円(20%)
• 合計:25万円程度
• 実費:郵送代や印刷代など、実際にかかる経費が別途発生する場合があります。
※以上のように、費用はさまざまな要素によって変わるため、具体的な見積もりは依頼を検討している弁護士事務所に直接問い合わせることをお勧めします。無料相談を行っている事務所も多いため、まずは相談してみると良いでしょう。
最後に
本記事では、借金の消滅時効についての基本情報や、時効援用の手続きについて詳しく解説しています。「借金の消滅時効とは何か」「時効が成立する条件」「援用に関する注意点」「時効以外の借金解決方法」「時効が成立しているかどうか確認するために弁護士に相談する価値」について解説しました。
この記事が多くの方々の借金時効援用手続きに役立つことを願っています。しかし、「最後の取引はいつだったか」と記憶が曖昧になることがよくあります。借金の督促状が届いたり、心当たりのない金融業者からの請求書が来たり、債権回収を行っている法律事務所から通知が届いた場合などは、自分で解決しようとせずに、弁護士に相談することをお勧めします。援用手続きなどを進めて実際に時効を成立させるためには、専門的な知識を持った弁護士のサポートが不可欠です。当事務所にご相談いただければ、もし時効が成立していなかった場合でも、債務整理についてのアドバイスや手続きを行うことが可能です。借金問題は早期に適切な対策を講じることで解決に繋がりますので、少しでも不安がある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
お問合せと時効援用の流れ
-
step.1お問合せ

お電話もしくはメールでご相談ください。
» -
step.2ご相談

お悩みやご心配事など何でもご相談ください。
解決策をご提案します。» -
step.3受任
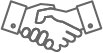
ご依頼(受任)となりましたら、あなたにピッタリな時効援用の方法で対応を進めます。
» -
step.4和解

あなたにあった借金の解決方法で時効援用。支払い方法などは、債務整理の内容で違いますが、借金がない生活を取り戻します。
苦しい返済からの解放。
面倒な手続きは全てお任せください。
